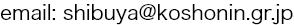はじめに
Introduction
このウェブサイトは、当渋谷公証役場の所在、概要、公証人の公証事務についての考えや当役場の取扱う公証事務の内容等について説明したものですが、記載事項、記載内容とも公証事務についての部分的な説明にとどまっています。
令和7年10月1日、改正された公証人法・公証人法施行規則・公証人手数料令が施行されました。
特に、電子公正証書制度が導入され、今後、極めて例外的な場合を除き、原本は電子的に記録・保存されることになります(当事者は、原本に署名押印できず、タッチペンで電子サインをします)が、電子公正証書の作成依頼、公証人との相談、予約に至るまでの手続は、これまでと大きく変わるところはありません。なお、正本・謄本については印刷した書面を交付することができます。
電子公正証書の作成に当たっては、対面方式とウェブ会議によるリモート方式がありますが、対面方式の場合はこれまでと大きく変わるところはありません。リモート方式の場合は署名用電子証明書等(通常は個人番号カードの電子署名)の提供により、本人であることを明らかにすることになりますが、具体的には、案件の依頼・相談の過程で公証人にお尋ねください。
公証事務全般について、あるいは公証事務についての技術的説明や具体的資料等、例えば、電子定款を作成して公証人の認証を受けるためのパソコンの環境設定その他の準備作業、電子定款認証の嘱託手順、会社の定款記載例、一般社団法人及び一般財団法人の定款記載例等をお望みの方は、日本公証人連合会のウェブサイト(https://www.koshonin.gr.jp/)をご覧ください。
また、私文書認証(特に外国向け文書の認証)に必要になる宣言書・委任状に関する説明やサンプルについては、東京公証人会のウェブサイト(https://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/foreign/)もご覧ください。
電子定款の認証は、法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用しますので、法務省のウェブサイト(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00003.html)の同システム及び電子公証に関する部分もお読みください。
 お知らせ -News & Information
お知らせ -News & Information
- ホームページをリニューアルしました。
利用者様にとって見やすくてわかりやすいホームページを目指して作りました。
 公証人あいさつ
公証人あいさつ
-Message from the Notary
※各項目をクリックすると、アコーディオンが開きます。
公証人
当役場の公証人は、次の5人です。
山 下 輝 年 (やました ・ てるとし)
吉 田 正 喜 (よしだ ・ まさき)
齊 木 教 朗 (さいき ・ のりお)
佐 藤 美由紀 (さとう ・ みゆき)
鈴 木 義 仁 (すずき ・ よしひと)
私達は、法令遵守で仕事をしますので、次の点をご理解願います。
◎皆様の作成したオリジナルの契約書に記載があっても、借地借家法や利息制限法、消費者契約法等の強行規定に違反する事項等は、公正証書には記載することができません。
◎公序良俗に反するような合意内容も公正証書化することはできません。
◎不法行為に対する損害賠償などで、賠償額が過大で、相手の非に乗じて大きな賠償額を承諾させたようなものも、同様です。
◎合意内容自体は不当でなくても、合意の成立過程や、相手方を役場に連れてくるのに無理強いをしているような場合も、お断りすることになります。
こうした疑いがあるときには、立ち入ってお尋ねすることになるかと思いますが、その点はご承知置き願います。
また、当役場には、書記が現在8人おり、私達は、書記の補助を受けながら、事務を取り扱っています。書記は、いずれも皆様への親切丁寧な応対を心がけ、誠実に仕事に取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。
当役場では、遺言、任意後見、離婚給付、定款の作成等に関する勉強会、講演会等への講師の派遣のご依頼があれば、公証人がご依頼にお応えすることにいたしていますので、ご相談ください。
手数料
公証事務の手数料については、このウェブサイトでも、個々の公証事務について説明する中で適宜触れていますが、十分ではありません。これについては、日本公証人連合会のウェブサイトの「手数料」のページに詳細な説明がありますので、それをご覧ください。
本人特定資料
1 電子公正証書制度の導入により、
(1)公証役場又は出張先で対面にて作成する方法(対面方式)
(2)ウェブ会議にて画面等を通じて作成する方法(リモート方式)
のいずれかで作成することになります。
上記(2)のリモート方式で作成する場合といいましても、電子公正証書作成時までに
(2a)当事者が一度又は数度来所する場合
(2b)依頼・相談全てメール等で行い、一度も対面せずにリモート方式で作成する場合(完全リモート方式)
の二つに分けられます。
2 「個人番号カード」(マインバーカード)による本人特定の推奨
上記1 (1)(2)(2a)(2b)のいずれの場合でも、改正公証人法28条により、当事者は、署名用電子証明書等(通常は個人番号カードの電子署名によるもの)を提供する方法で嘱託人が本人であることを明らかにすることができるようになり、また、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付率も8割以上と普及していますので、個人番号カード(マイナンバーカード)をご用意することをお勧めします。
3 対面方式とリモート方式における本人特定方法
対面方式の場合、電子公正証書作成時には個人番号カード原本を公証人に提示することで本人確認ができますので、これまでの取扱と大きく変わるところはありません。(ア)顔写真付き公的身分証明書(運転免許証、パスポート等)、(イ)印鑑登録証明書と実印(その実印による嘱託書類への押印)でも可能です。ただし、写しを事前に提供していただくことが事前の円滑な準備に役立ちます。
リモート方式のうち、(2a)の場合は、一度面談する際に、個人番号カード、その他上記(ア)(イ)の原本を提示又は提供することができますので、その際に本人特定ができます。
一方、(2b)の完全リモート方式により電子公正証書を作成する場合、本人特定については、身分証明書を画面で提示することになるため、本人特定は不十分となりますので、署名用電子証明書が不可欠となり、電子公正証書作成依頼書(申込書)等に電子署名したものを電子メールにて送信することが必要です。なお、事前に個人番号カード表面の写しを電子メールにて送信していただきます。
4 極めて例外的に書面にて公正証書を作成する場合
この場合には、これまでと同様であり、上記3 (ア)(イ)の方法により本人特定できますが、パスポートの場合は、住所表記も氏名の漢字表記もありませんので、住民票等の補足資料が必要となります。
5 私署証書認証・定款認証の場合
電子公正証書以外の私署証書認証や定款認証の場合、これまでの取扱に変更はありませんので、日本公証人連合会・東京公証人会・本ウェブサイト「手続一覧」をご覧ください。
◎公証人及び書記
公証人紹介や公証人の仕事、各種手続についてのページです。公正証書作成・遺言・離婚・任意後見・契約・定款認証・確定日付などはこちらをご覧ください。
◎執務日及び執務時間
午前9時~午後5時です。(月~金曜日、除く祝日及び年末年始休業日)※受付時間は、原則として、
・午前9時から午前11時まで
・午後1時から午後4時まで
住所、執務時間、受付時間など、渋谷公証役場についてのご案内のページです。いつでもお気軽にいらしてください。公証業務に関する相談を承ります。
◎委任状(鑑文書)サンプル集
渋谷公証役場がお勧めする委任状の作り方やサンプル集のページです。